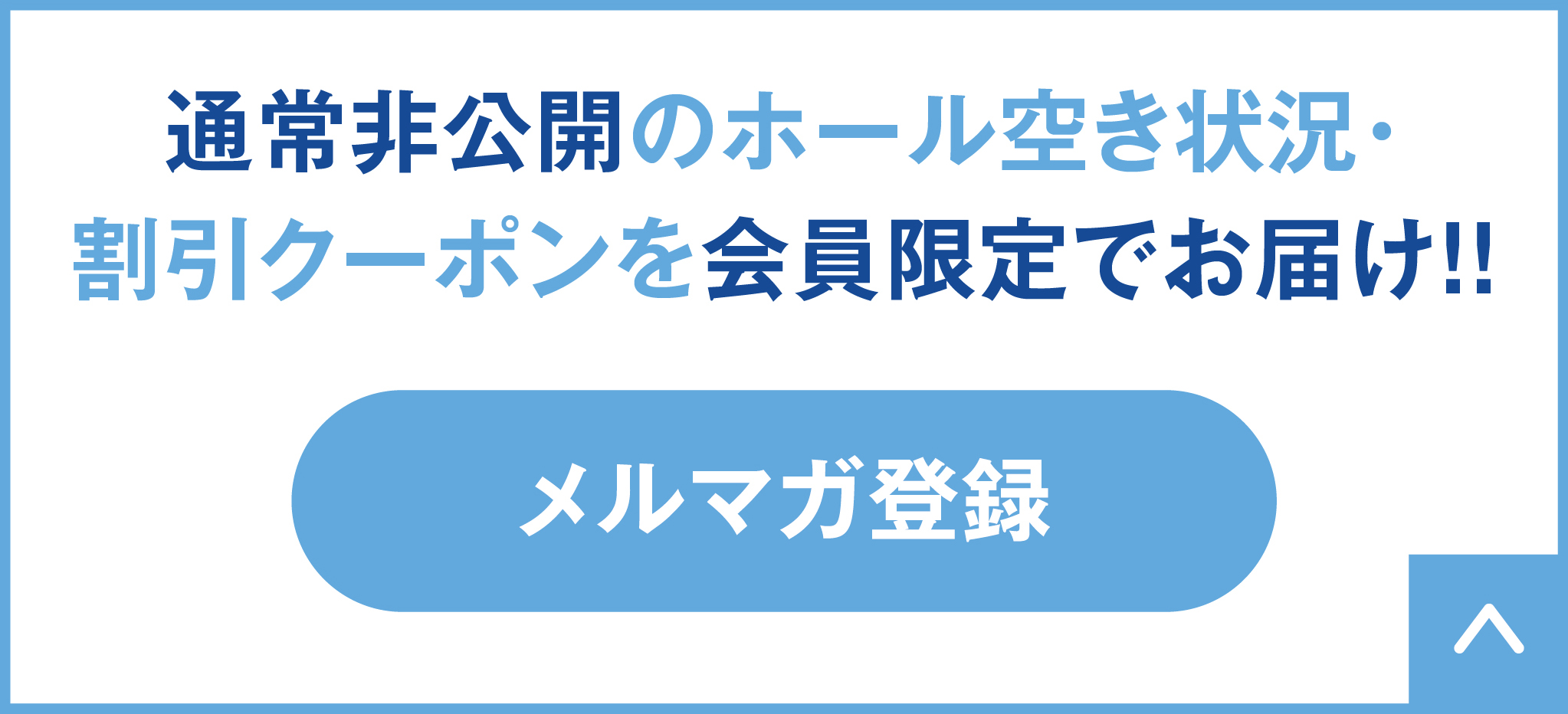2020.12.02
【東京】コロナ禍でも使える!試験会場の探し方
- 主催者向け
- 東京
- 試験会場


2020年に入ってから、新型コロナウイルス感染症対策として試験会場の変更を余儀なくされるケースが増えています。「試験会場として使う予定だった大学や東京都などの自治体が運営する施設が使えなくなった」という方も多いのではないでしょうか。今回は、コロナ禍でも安心して利用できる試験会場の探し方や感染予防対策についてお伝えします。
- 目次
試験会場の選び方5つのポイント

展示会場、貸し会議室などさまざまなタイプのレンタル会場がありますが、「どういった点に着目して試験会場を選べばいいのかわからない」という担当者の方も多いかと思います。ここでは、試験会場の選び方のポイントをご紹介します。
アクセスと広さを重視
試験会場を選ぶ際は立地が重要なポイントとなります。受験者が迷って遅刻するリスクを減らすためにも駅から近い場所を選ぶと親切です。感染症対策として受験者同士のソーシャルディスタンスを確保する必要もあるので、収容人数を考える際はそのことも考慮し、広い会場を選びましょう。
周囲の環境もチェックする
試験においては周囲の環境も大切です。落ち着いた環境で試験に臨めるよう、できれば繁華街から離れた静かなエリアを中心に会場を探しましょう。人混み・繁華街を避けることで受験者が会場に向かう際に3密空間に巻き込まれるリスクも減り、感染症対策にもつながります。
備品・機材は足りているか
試験ではイスや机、アナウンス用のマイクなどさまざまな設備が必要です。これらの機材が「会場でレンタル可能か」「数は足りるのか」といった点をしっかりと確認しておきましょう。
控室をレンタルできるか
もしスタッフ用の控室を用意する必要がある場合は、別の会議室などをレンタルできるかチェックしておきましょう。予約が入っているなどの理由でレンタルができなかった場合は、イベント会場の一部を区切って控室を作ることで対応も可能です。
可能な限り下見を行う
ホームページやパンフレットの情報だけではわからないことも多々あります。駅からの道順、入口からの動線、受付場所、トイレの場所、会場側で行っている感染症対策の情報などをチェックするためにも可能な限り下見を行うのがベストです。下見を行うことで試験当日の座席のレイアウトや当日の進行方法をより具体的に考えることができるでしょう。
コロナ禍における試験の実施事例
2020年のコロナ禍で実施された試験の事例をご紹介します。
税理士試験
2020年度第70回税理士試験では、ソーシャルディスタンスを保てる会場を使用するため急遽会場が変更されました。当初は全員幕張メッセで試験が行われる予定でしたが、変更後は一部の受験生が「TOC五反田」「TKP市ヶ谷カンファレンスセンター」「横浜アリーナ」の3会場に割り振られています。試験直前に会場変更が行われたため、混乱した受験生もいたとのことです。感染症対策としてはサーモグラフィーによる検温が行われ、マスク着用、アルコール消毒を呼びかけました。
―令和2年度税理士試験終了!コロナ禍は本番にどう影響した?
https://kaikeizine.jp/article/18457/
―令和2年度(第70回)税理士試験の試験場の変更(千葉県「幕張メッセ」会場の受験者)について
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/0020008-026.htm
英検
2020年度第2回英検では、試験会場内の混雑を緩和するために級ごとに試験の開始時間を変更しました。また、来場前のヘルスチェック、マスクの着用、来場時の手指の消毒、最低人数での来場、保護者控室の設置をなくすなどの感染症対策が行われました。
―「英検(従来型)本会場」における新型コロナウイルスへの対応
https://www.eiken.or.jp/eiken/healthcheck2020.html
知的財産管理技能検定
第36回知的財産管理技能検定では、受験者の対面形式での着席を取りやめ、3密を避けたレイアウトで行われました。座席もソーシャルディスタンスを意識し、1メートル以上空けて配置しました。そのほかにもマスクの着用、当日の検温、手指の消毒、試験日前2週間の状況報告などが実施されたとのことです。
―検定実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み
http://www.kentei-info-ip-edu.org/torikumi.html
コロナ禍で使える!試験会場設営のポイント

試験会場設営時に意識すべきポイントについて解説します。
ソーシャルディスタンスの確保
筆記試験を受ける際に受験者が座る座席は、間隔を1メートル以上空けて設置しましょう。また、エレベーターホールや受付などでもソーシャルディスタンスを維持できるよう足元に目印となるカラーテープを貼ると効果的です。
消毒用アルコールを準備する
受付や入口付近にアルコールを設置し、手指を消毒してもらいましょう。配布物がある場合はスタッフが渡すのではなく、受験者自身に取ってもらうようにするのがポイントです。
マスク着用や検温を義務化する
試験当日までにマスク着用がルール化されていることを周知しておきましょう。当日もしマスクをつけていない受験者がいた場合は、受付でマスクを配布できるように準備しておくと安心です。また、会場の受付などでは、検温を行いましょう。
技能検定の実施に関する感染拡大防止ガイドライン
厚生労働省が2020年5月に「技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」を発表しています。このリリースを参考にして試験会場づくりやスタッフの教育に。
|
【技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン】※一部抜粋
▼1 受検申請時の対応 技能検定の受検申請は、窓口での受付は控え、原則として、郵送又はオンラインにより受付を行うこと。やむを得ず窓口での受付を行う場合は、以下の対応を採ること。
・ 整理券の配布等により受検申請者の行列の発生を防止すること。 ・ 受付時には、申請書類の受取にとどめ、書類の確認は追って行うこととし、必要があれば、受検申請者に電話等で追加提出・修正等を依頼すること。 ・ 待機時等に受検申請者同士が接近することがないよう、十分な間隔を取ることができるように誘導すること。 ・ 受検申請者に、手洗い、アルコール消毒、マスクの着用等の感染防止対策を勧奨すること。受付担当職員にも、手洗い、アルコール消毒、マスクやフェイスシールドの着用等の感染防止対策を徹底すること。
▼2 定期実施試験(学科)の対応
(1)受検者、検定委員及び補佐員等への依頼事項 ア 試験会場における感染拡大防止措置への協力 イ マスクの持参及び会場内でのマスクの着用 ウ 会場におけるこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施 エ 試験当日の体温の報告及び確認 オ 試験日前2週間における以下の事項の報告及び確認 (ア)平熱を超える発熱 (イ)咳、のどの痛みなどの風邪の症状 (ウ)だるさ(倦怠感)、息苦しさ (エ)嗅覚や味覚の異常 (オ)身体が重く感じる、疲れやすい等 (カ)新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 (キ)同居家族や身近な知人の感染が疑われる方の有無 (ク)過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触の有無
(2)試験会場での対応 ア 試験会場の入口及び施設内に、石けん及び消毒用アルコールを設置する等、手指の衛生を保つことができる環境を整備すること。
イ 適切な環境維持のため試験会場の換気を心掛けるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて湿度、温度の管理に努めること。学科試験中においても、試験の実施に支障が生じない範囲で換気に努めること。
ウ 学科試験の配席に当たっては、原則として受検者相互に2メートルの間隔を取るように配席を行うこと。会場確保上2メートルの間隔を取ることが困難な場合であっても、少なくとも1メートルの間隔を取るようにすること。
エ 試験会場内の休憩スペース、食事スペース等において人が密集することがないよう、一度に使用する人数を減らす、相互に間隔を取らせる等の措置を採ること。
オ 試験会場内での人の移動により受検者等が密集することのないよう、入室、退室を一斉に行わせないこと。
カ 受検者に発熱等の症状がみられた場合は、当該受検者の状況を総合的に勘案し、必要に応じて受検の自粛を申し入れること。
▼3 定期実施試験(実技)の対応
(1)受検者、検定委員及び補佐員等への依頼事項 ア 試験会場における感染拡大防止措置への協力 イ マスクの持参及び会場内でのマスクの着用 ウ 会場におけるこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施 エ 試験当日の体温の報告及び確認 オ 試験日前2週間における以下の事項の報告及び確認 (ア)平熱を超える発熱 (イ)咳、のどの痛みなどの風邪の症状 (ウ)だるさ(倦怠感)、息苦しさ (エ)嗅覚や味覚の異常 (オ)身体が重く感じる、疲れやすい等 (カ)新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 (キ)同居家族や身近な知人の感染が疑われる方の有無 (ク)過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触の有無
(2)試験会場での対応 ア 試験会場の入口及び施設内に、石けん及び消毒用アルコールを設置する等、手指の衛生を保つことができる環境を整備すること。
イ 適切な環境維持のため試験会場の換気を心掛けるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて湿度、温度の管理に努めること。実技試験中においても、試験の実施に支障が生じない範囲で換気に努めること。
ウ 実技試験の受検者の配置に当たっては、原則として受検者相互に2メートルの間隔を取るように配置すること。会場確保上2メートルの間隔を取ることが困難な場合であっても、少なくとも1メートルの間隔を取るようにすること。受検者間にアクリル板、透明ビニールカーテン等を設置することも有効であるが、実技試験の作業内容によっては可燃物を使用することにより火災を発生させるおそれがあるので、事前に安全性を検証すること。
エ 実技試験において共用する機器については、原則として受検者が使用するたびに消毒すること。
オ 試験会場内の休憩スペース、食事スペース等において人が密集することがないよう、一度に使用する人数を減らす、相互に間隔を取らせる等の措置を採ること。
カ 試験会場内での人の移動により受検者等が密集することのないよう、入室、退室を一斉に行わせないこと。
キ 受検者に発熱等の症状がみられた場合は、当該受検者の状況を総合的に勘案し、必要に応じて受検の自粛を申し入れること。
▼4 随時実施試験の対応 定期実施試験(学科・実技)の対応に加え、受検者が日本語を母国語としないことを踏まえ丁寧に対応すること。
▼5 合格発表時の対応 原則としてホームページ、郵送等により発表すること。庁舎内の掲示板等での発表は 受検者の密集を招く可能性があるので実施しないこと。
▼6 技能検定関係者の健康管理
(1)都道府県、都道府県職業能力開発協会及び指定試験機関 都道府県、都道府県職業能力開発協会及び指定試験機関は、技能検定に関する業務に従事する職員等の健康管理に努め、その業務において新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを減少させる取組を行うこと。
また、職員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は濃厚接触者となった場合等を想定した技能検定の実施体制を検討しておくこと。
(2)職員等 技能検定に関わる都道府県職員、都道府県職業能力開発協会職員、指定試験機関職員、検定委員及び補佐員等は、自身の健康管理に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めること。 |
厚生労働省発表の「技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」を確認
下記のリンクにより詳しい内容が記載されています。ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000639207.pdf
適切な感染症対策を心がけよう

この記事を参考にコロナ対策を行って
受験者に安心してもらえる試験会場づくりを心がけよう