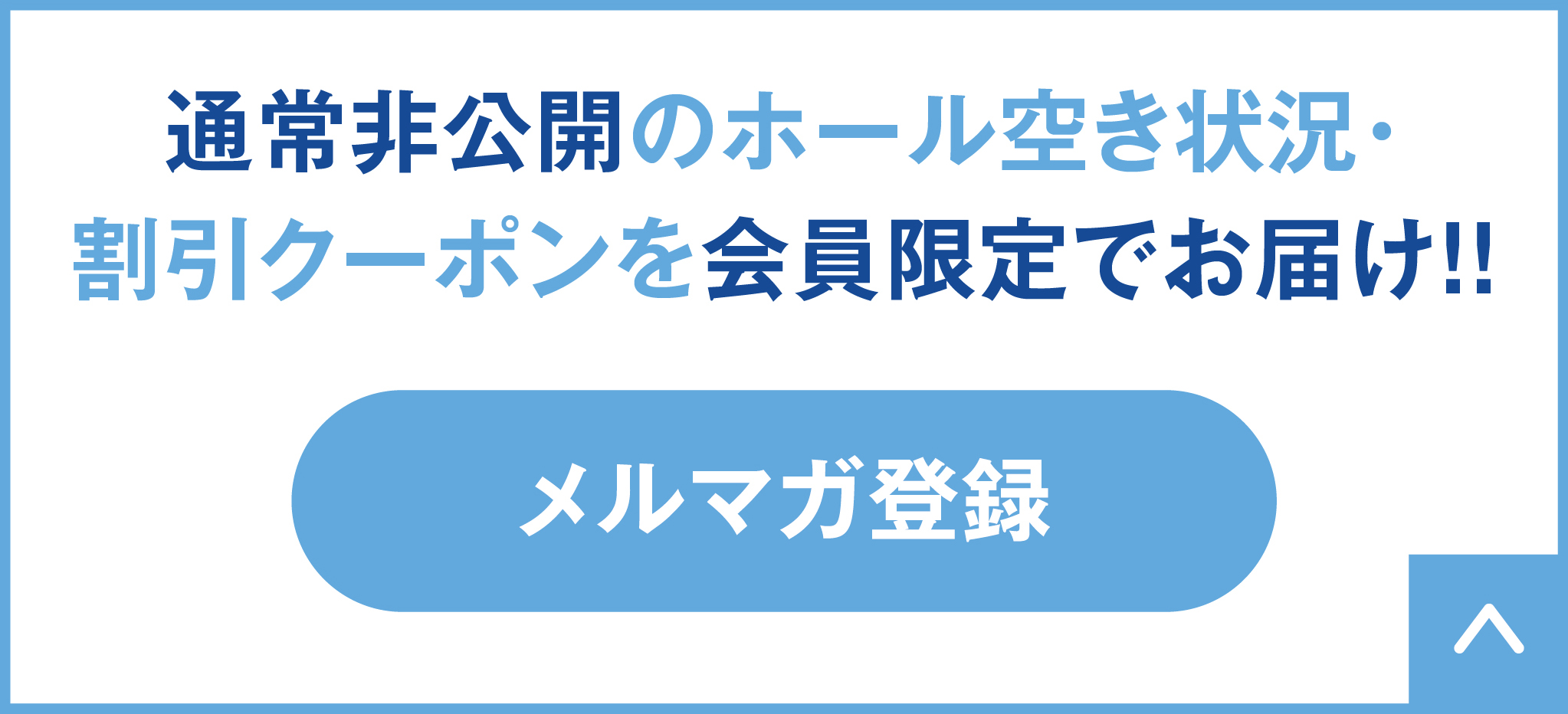2020.10.19
コロナ禍でのイベント・展示会のガイドライン作成のポイント
- 展示会
- コロナ
- コロナ対策
- イベント
- ソーシャルディスタンス
- マスク
- 消毒
- 検温
- 3密
- 飛沫防止


2020年10月現在、新型コロナウイルスの感染は依然として収束していません。こういった緊急事態により予定していたオフラインイベントで、新たにガイドラインを作る必要が出てきたイベント主催者の方も少なくないのではないでしょうか。今回はオフラインでのイベント・展示会の開催を検討している方に向けて注意点や、ガイドライン作成時のポイントをご紹介します。
- 目次
イベント開催前の注意点

来場者が集まりづらい
2020年現在多くのイベントが延期・中止・オンラインイベント化を余儀なくされています。どのようなイベント・展示会であっても参加を控える人が多いのが現状です。たくさんの来場者を迎えることが難しいということを念頭に置きましょう。
イベント開催そのものを批判されるケースがある
オフラインイベントの開催発表時にインターネットや電話等を通じて批判意見が集まることも考えられます。行政やイベント会場のガイドラインに従って、できる限り安全なイベント開催を心がけても、批判を受けてしまう可能性があることは念のため考慮しておきましょう。
来場者の行動・連絡先を可能な限り把握する
来場者やスタッフの氏名と連絡先を可能な限り把握しておきましょう。来場者に対して「新型コロナウイルス接触アプリ(COCOA)」をインストールするよう促すのも効果的です。「COCOA」では、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取ることができるようになっています。
「新型コロナウイルス接触アプリ(COCOA)」について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000642043.pdf
イベントへの参加料・入場料についての規定を設ける
スタッフとの接触機会を減らすため、可能な限り事前決済を行いましょう。当日に支払いが発生する場合はキャッシュレス決済の導入を検討し、入場を断る際の返金規定も設定してください。
参加人数がキャパシティーを超えないようにする
複数人が集まってしまうとクラスターが発生するリスクが高まります。イベントを行う際は主催者側で来場人数が会場のキャパシティーを超えないよう管理を徹底しましょう。来場者とスタッフの接触も最小限にするよう工夫していく必要があります。
ソーシャルディスタンスの確保
会場レイアウト・動線づくりにおいてソーシャルディスタンスの確保を意識しましょう。ソーシャルディスタンスの目安は約2mです。行列ができるブースや受付などにはテープやサインを設置して、間隔を空けて並んでもらえるように準備しましょう。
イベント当日の注意点

マスク・消毒の徹底
来場者にマスク着用を周知し、手指を消毒してもらいましょう。また、人の手が触れる場所も消毒を行いましょう。イベント開催中の時間であっても、公演・プレゼンテーションの来場者入れ替え時の座席や、多くの人の手が触れるテーブル、ドアノブ、パソコン、マイクなどは適宜消毒してください。
入場時に検温を行う
イベントの入口で来場者の検温を行いましょう。スタッフや出演者を含め体調不良者は出席を見送る必要があります。目安としては37.5℃以上の方に参加を見送ってもらうのが一般的です。体温計、サーモグラフィーカメラ、検温ゲートなどを利用してしっかりと検温を行いましょう。
参加できない方へのフォローを準備する
体調不良や自粛のため当日参加できなかった方のためにフォローがあると親切です。プレゼンテーションなどの発表内容を動画や写真等を使って配信しましょう。
3密にならないよう誘導スタッフを配置
会場内のソーシャルディスタンスに気を配っていても、エレベーターや待機場所等が密になってしまうケースがあります。混雑が予想される場合はエレベーターやエスカレーター、会場入口付近にもスタッフを配置し、列の誘導を行いましょう。
講演台に飛沫防止のシールドを装着する
セミナー、式典等で講演台を使う場合は飛沫防止のシールドを設置しましょう。登壇者と聴講者が座る最前列の席は2m離すことが推奨されています。聴講者の座席の間隔は前後1m、左右1名分程度の間隔を空けてください。
搬入・搬出時や休憩時もコロナ対策に気を抜かない
施工や運送関係のスタッフにもマスク着用を依頼し、会場の風通しをよくすることを心がけてください。3密防止のアナウンスは常に行い、搬入・搬出時も消毒液を入口に設置しましょう。スタッフの休憩時間にも気を配ることが大切です。
日本展示会協会のクイックリファレンスを参考にしよう
一般財団法人 日本展示会協会でイベント開催時のガイドラインを発表しています。ご参照ください。(※このクイックリファレンスは2020年8月17日発表のものです。)
https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/200827_quickreference.pdf
展示会・イベント会場のガイドライン作成のポイント
2020年9月11日から、イベント開催の制限が緩和されました。ここでは大声での歓声・声援がないことを前提とするイベント(公演、式典、商談会、展示会など)を開催するにあたって、確認しておきたいポイントをご紹介します。(※記載の内容は2020年9月11日時点に内閣官房が発表した内容を参考にしています。)
収容率
| 時期 | 収容率 | 人数上限 | |
| 当面2020年11月末まで | イベントの類型 |
大声での歓声・声援がないことを前提とするイベント 100%以内 |
①収容人数10,000人超 ⇒ 収容人数の50% ②収容人数10,000人以下 ⇒ 5,000人 ※収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度とする。 |
イベント開催制限の緩和に伴う措置について
・消毒の徹底・マスクの着用
感染リスクを下げるため、消毒とマスクの着用を徹底しましょう。また、マスクを持参していない来場者がいた場合は主催者がマスクを配布し、着用率100%を担保しましょう。
・来場者・出演者への対応
すべての来場者・出演者に対して検温を実施し、体調不良の方の来場・出演は控えてもらいましょう。主催者側がチケット等の払い戻しについても規定しておくことが必要です。
・来場者の把握
事前予約時や来常時に、連絡先を書いてもらいましょう。また、接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスのダウンロードを促進しましょう。具体的にはアプリのQRコードを入口に掲示するなどの告知を行ってください。
・大声の抑止
スタッフによる大声の声かけは禁止しましょう。もし大声を出す方がいた場合は個別に注意し、対応できるようあらかじめスタッフを配置してください。
・3密の回避
来場者の入退場列や休憩時間も3密を回避し、常に十分な換気を行いましょう。食事等での感染にも気を付けてください。3密が回避できない場合は、目安の人数上限を下回るよう制限内容を変更してください。
・飛沫感染リスクの排除
来場者と出演者が公演の前後や休憩時間等に接触しないように徹底してください。接触が防止できない場合は開催を見合わせる必要があります。
・イベント前後の行動管理
3密回避のため、交通機関・周辺の飲食店を分散して利用するように注意喚起してください。主催者あるいは施設管理者が予約システム等をもうけ、来場者の分散利用を促進しましょう。
詳細は内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」ページを確認
下記のリンクにより詳しいルールが記載されています。ご参照ください。(※この資料は2020年9月11日発表のものです。)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
会場や関係会社とも協力し、安全なイベント開催を心がけよう

対策を徹底したうえでオフラインイベントを行おう
行政が発信する最新情報を常に確認してね